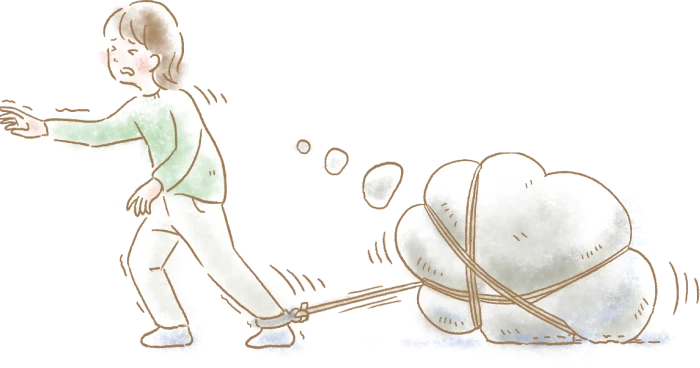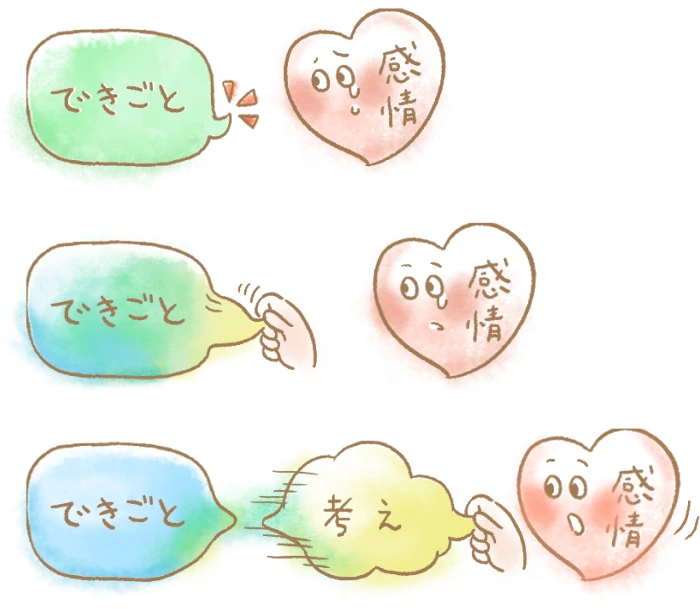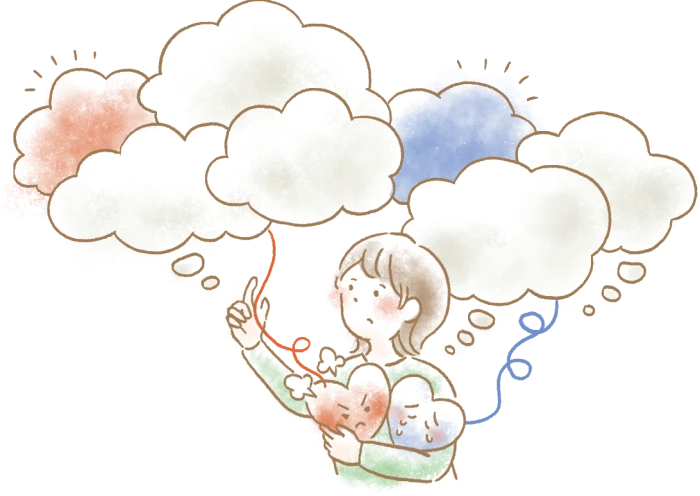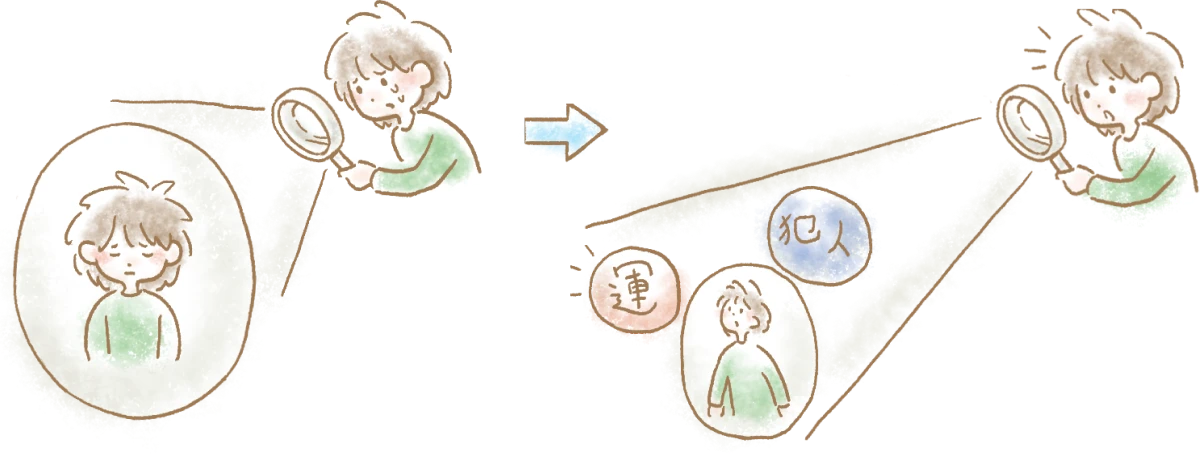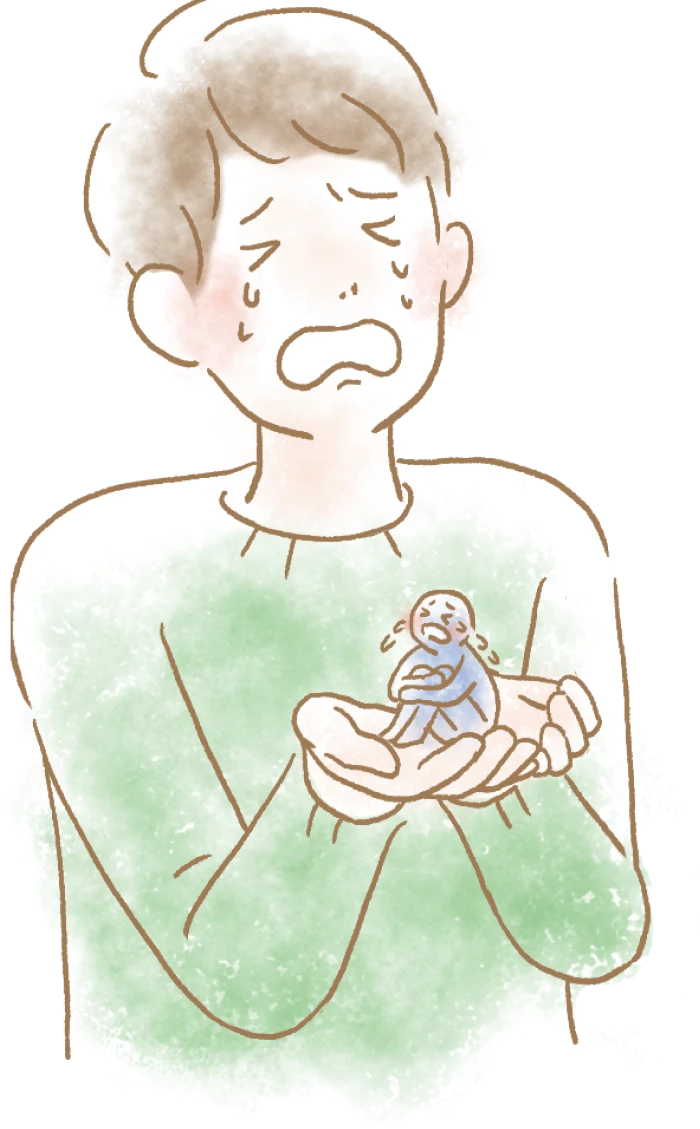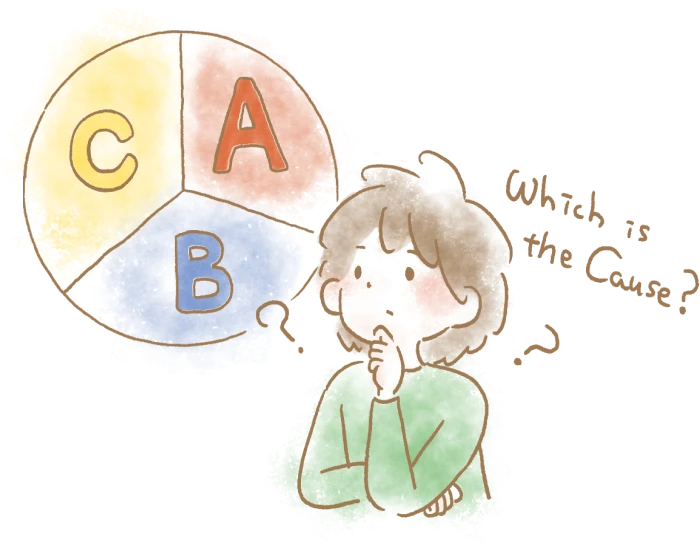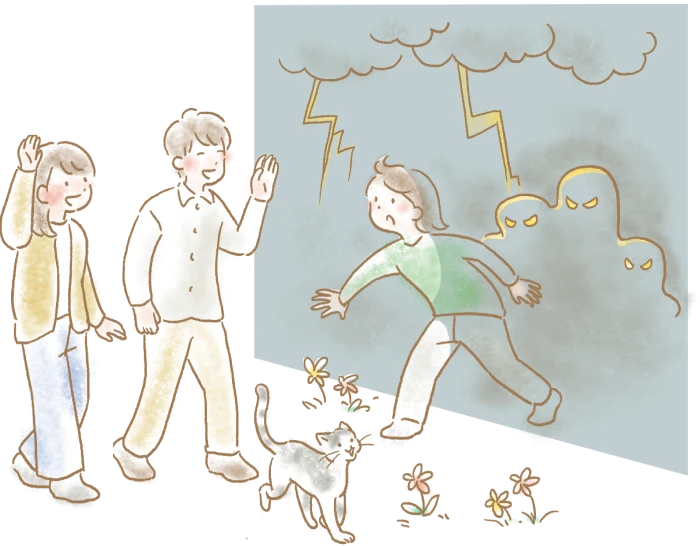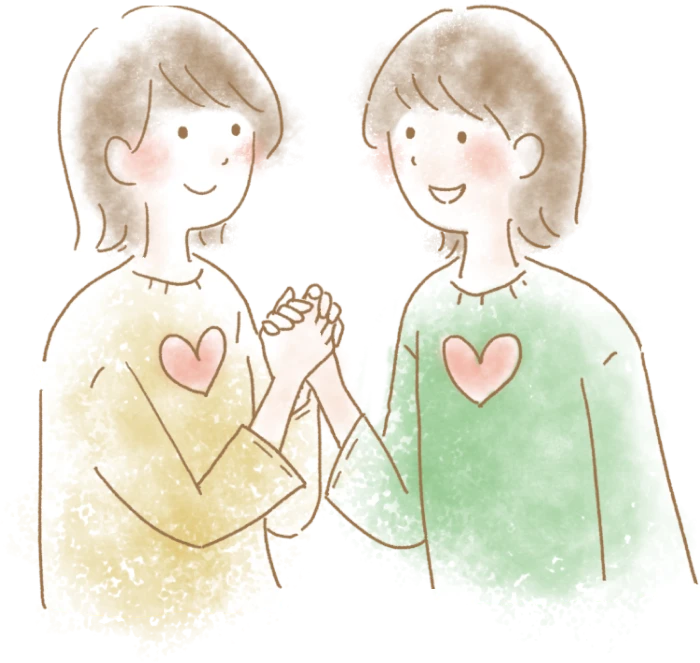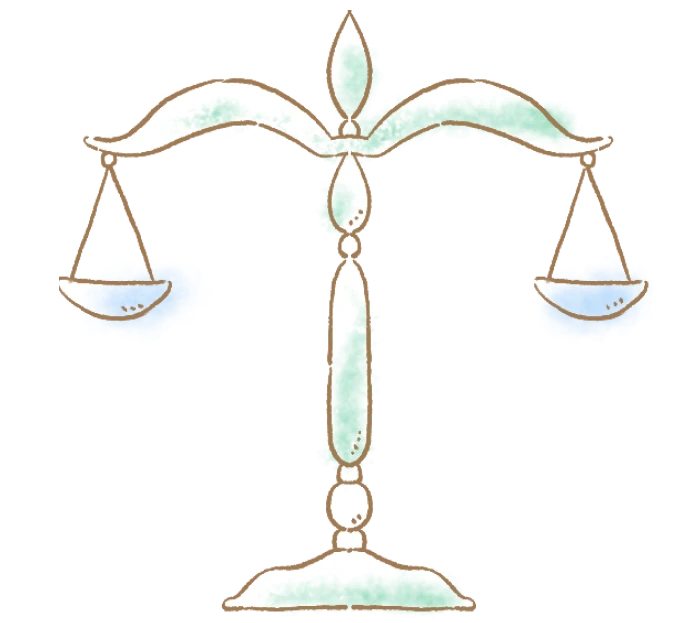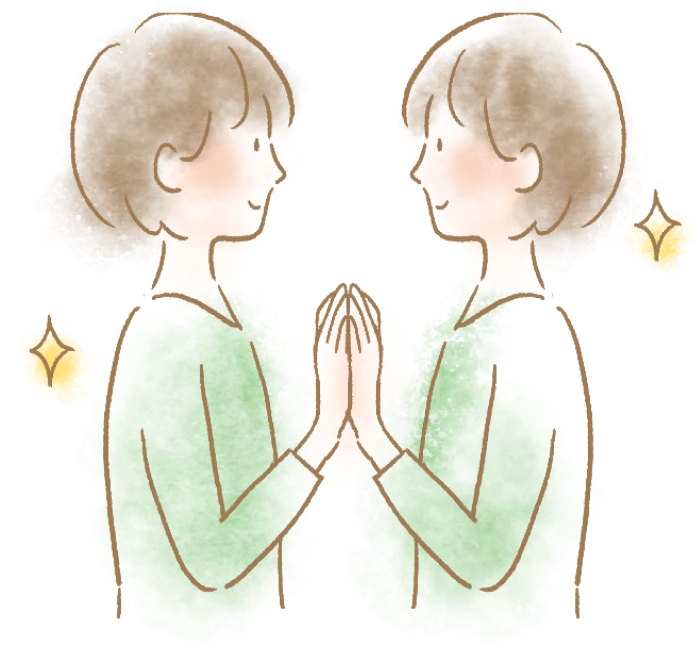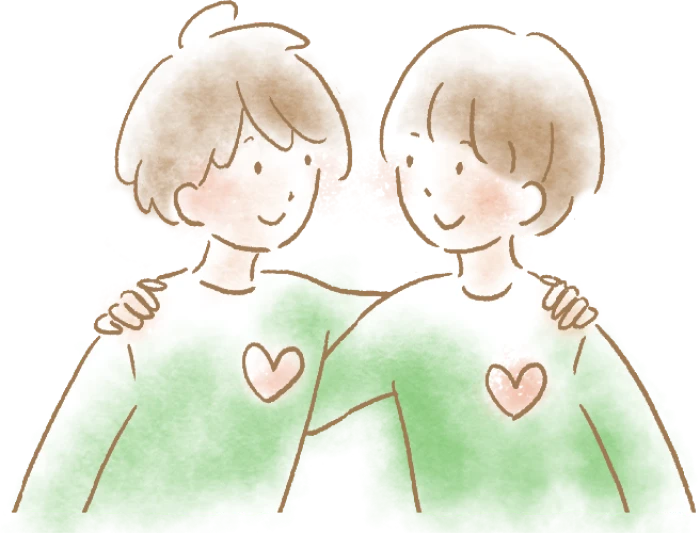治療をはじめる前に
CPTは、PTSDや関連する症状の改善に効果な治療法であり、万能ではありません。そのため、CPTをはじめた方が良いか、もっと別の対応が適するか、支援を求める人と治療提供者とで検討することが必要です。
CPTをはじめるまでのステップ
- . PTSDや、同時に抱えている問題について情報を集め、PTSDの治療に取り組む方が良いか判断する
- . PTSDの治療の選択肢を比較して、これから取り組む治療法を選ぶ
- . 治療を求める人と治療を提供する者の間で、治療の進め方について契約を結ぶ
CPTでは、セッションを進めながら、治療の支えとなる「安全で健全な関係づくり」を行うため、治療提供者との関係作りだけを目的としたセッションは不要とされます。一方で、治療に安心して取り組める環境を整えることや、PTSDでお困りの方ご本人が治療に取り組みたい意欲をお持ちかどうかは、とても大切です。治療に取り組む準備が整っているか、丁寧に確認した上ではじめられることをおすすめします。